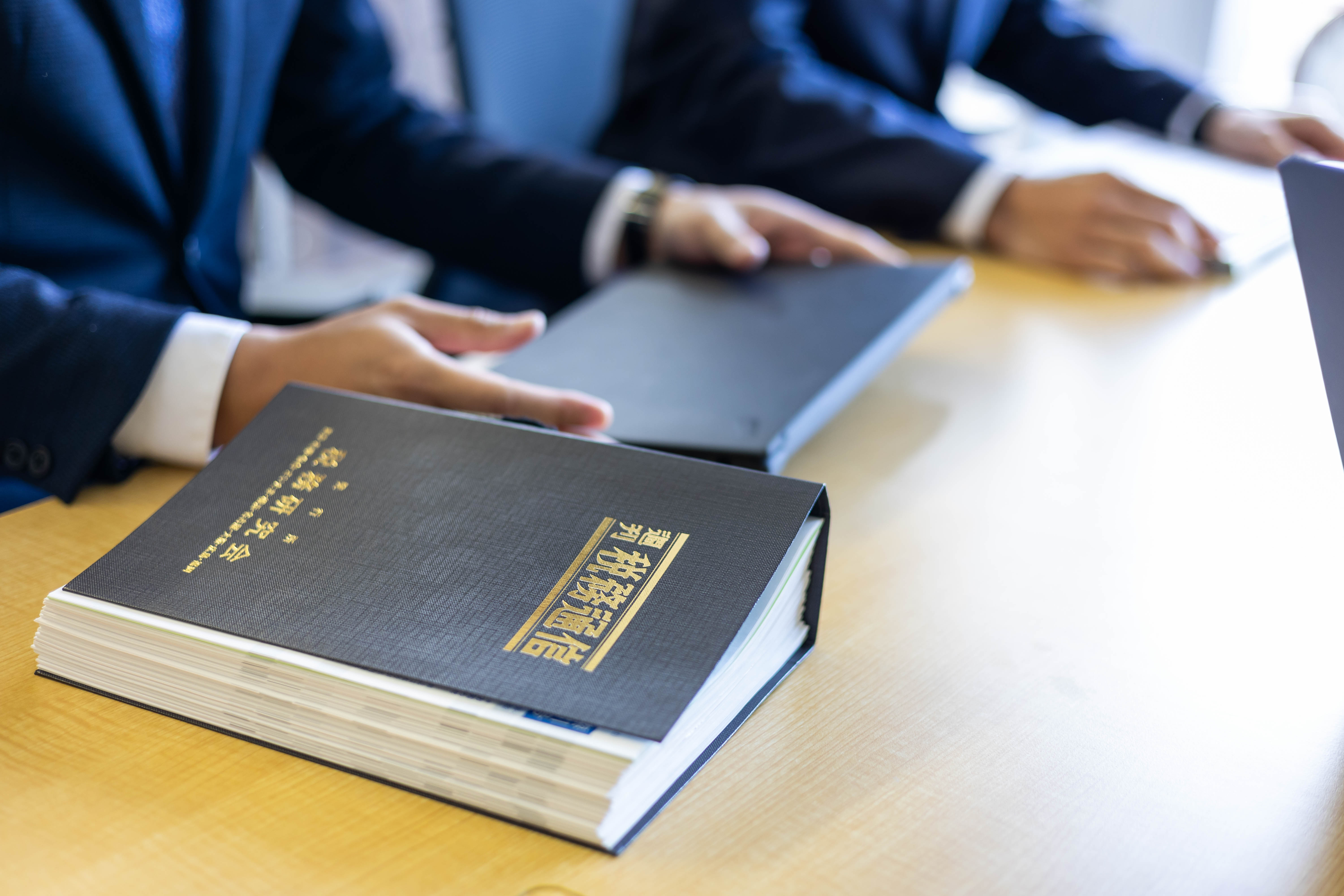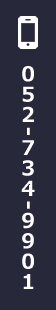2025年度(令和7年度)税制改正により、退職所得控除に関する特例「5年ルール」が、「10年ルール」へと変更されることが決まりました。特に、会社の退職金とiDeCo(個人型確定拠出年金)など、複数の退職金等を別々の年に受け取る人にとっては、税額に大きな影響を及ぼす変更です。今回は、この新たなルールについてわかりやすく解説していきます。
〈そもそも「5年ルール」とは?〉
退職金は、給与所得とは異なり「退職所得」として扱われ、退職所得控除という大きな税制優遇を受けられます。
退職所得控除の基本計算式は次の通りです:
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円 ×(勤続年数−20年) |
同じ人が、例えば会社の退職金とiDeCoの一時金を別々の年に受け取った場合、原則としてそれらは勤続年数を通算して退職所得控除を計算します。
しかしこれには特例があり、最初の退職金の受取から5年超経過していれば、それぞれ別の退職として扱い、控除も個別に使えるというのが「5年ルール」でした。
ところが、2025年からはこの「5年ルール」が見直され、10年経過しなければ別枠で控除できないことになります。
〈「10年ルール」適用の有無による控除額の違い〉
以下に、実際のケースをもとに10年ルール適用の有無によって控除額がどう変わるのかを見てみましょう。
①:10年以内に受け取った場合(通算扱い)
-
退職A:60歳で退職、勤続30年、退職金:2,000万円
-
退職B:65歳でiDeCo受取、加入15年、受取額:500万円
-
合計退職金:2,500万円
-
勤続年数:30年+15年=45年
【退職所得控除額】
-
20年分:40万円 × 20年=800万円
-
残り25年分:70万円 × 25年=1,750万円
-
合計控除額:2,550万円
※退職金2,500万円に対して控除額が上回るため、課税所得ゼロ(非課税)
②:10年超経過して受け取った場合(別枠扱い)
-
退職A:60歳で退職、勤続30年、退職金:2,000万円
-
退職B:71歳でiDeCo受取、加入15年、受取額:500万円
【退職Aの控除額】
-
20年分:800万円
-
残り10年分:70万円 × 10年=700万円
-
合計:1,500万円
【退職Bの控除額】
-
40万円 × 15年=600万円
【合計控除額】=2,100万円(退職金合計2,500万円に対して控除が劣る)
→ 課税退職所得:400万円 × 1/2 = 200万円が課税対象
〈まとめ:分けるか通算か、節税効果はケース次第〉
この計算例では、通算扱い(10年未満)の方が控除額が大きく、税金を抑える結果となりました。これは、勤続年数を通算して45年とした場合の控除額が非常に大きくなるためです。しかし、すべてのケースで通算が有利とは限りません。
-
1回目の退職金が少額(早期退職など)
-
2回目の退職金(iDeCoなど)が高額
-
勤続年数を通算しても20年に満たない
といったケースでは、10年超経過して別々に控除した方が有利になることがあります。ご自身の状況に応じて最適な受取方法を選択するようにしましょう。